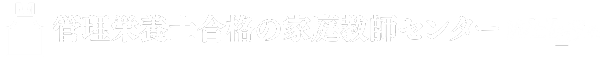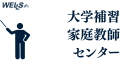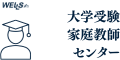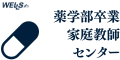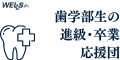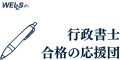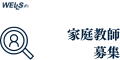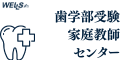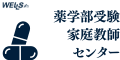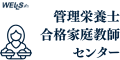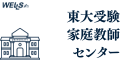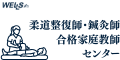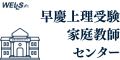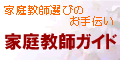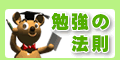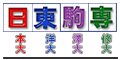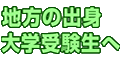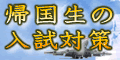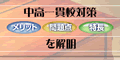栄養士から管理栄養士になるための考察
管理栄養士は、国家資格として栄養学に基づく高度な専門知識を活かし、医療・福祉・食品産業・行政など多分野で活躍します。業務は栄養管理だけでなく、個別化医療(病態に応じた栄養介入)、健康政策・地域栄養施策、食品機能の評価、疫学・調査研究にも及びます。医療・介護の現場では病態栄養に基づく栄養アセスメントと介入を多職種連携で実施します(NST 参画等)[出典1・5]。
さらに、食育・地域栄養、特定保健指導(メタボ予防)やスポーツ栄養など、活動領域は制度面の整備とともに拡大しています[出典1・4]。
1. 管理栄養士国家試験の受験要件(公式要領)
管理栄養士になるには、受験資格を満たして国家試験に合格する必要があります。受験資格は修了課程により異なります[出典2]。
(1) 栄養士養成施設卒業者(短大・専門学校・4年制栄養士課程など)
「修業年数」+「栄養士としての実務経験」=通算5年以上で受験可能
- 2年課程 → 実務3年以上
- 3年課程 → 実務2年以上
- 4年課程 → 実務1年以上
(※実務として認める施設・業務の範囲は受験要領に定義)[出典2]
(2) 管理栄養士養成施設卒業者(4年制大学の管理栄養士課程)
実務経験なしで受験可(卒業見込を含む)[出典2]
2. 実務経験の認定例と意義
受験要件における栄養士としての実務には、以下のような業務が該当します(例示)。
- 医療・福祉:病態栄養管理、NST活動、個別栄養指導・給食管理 等[出典1・5]
- 学校・給食施設:献立作成、栄養量設定、衛生管理 等[出典3]
- 行政:地域の栄養相談、健康・食育事業の推進 等[出典4]
- 食品産業:商品開発、品質管理、消費者相談 等[出典1]
実務は単なる年数の充足ではなく、臨床・公衆栄養・マネジメントの実践力として合格後の即戦力につながります。
3. 試験の難易度と最新の合格率
- 直近の合格率(全国)は
第39回(2025)48.1%/第38回(2024)49.3%/第37回(2023)56.6%。年により約48〜57%で変動しています[出典6・7・8]。 - 区分別(第39回)は、新卒(管理栄養士課程)80.1%、既卒(管理栄養士課程)11.1%、既卒(栄養士課程)11.7%。従来よく見かけた「既卒20〜30%」という表現は最新公表値と乖離します[出典6]。
4. 出題範囲と学術的対策(枠組みベース)
出題範囲:9科目+応用力試験/計200問。合格基準は200点満点中120点以上です[出典2・6・9]。
- 基礎・応用栄養学:代謝・エネルギーバランス・疾病予防の栄養学
- 食品学・食品衛生:機能成分・食品安全・微生物制御
- 公衆栄養/社会・環境と健康:疫学・政策・栄養疫学
- 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち/解剖生理・生化学
- 臨床栄養/栄養教育論/公衆栄養学/給食経営管理論 ほか
学習戦略は、(a) 科目横断の概念統合、(b) 過去問→解説→再演習の反復、(c) 頻出・計算・応用問題の重点化が定番です。応用力試験(状況設定)に向け、思考・判断プロセスを鍛えます[出典9]。
5. 個別指導の活用(働きながら合格するために)
- 論理的解説で背景理論をつなげ、読解・計算・根拠提示の力を底上げ
- 弱点特化の計画最適化(進捗可視化・復習間隔設計)
- 演習ベースの時短(本番フォーマットでの解法訓練)
忙しい社会人・学生でも、限られた時間で点に直結する学習を設計できます(枠組みは出題基準・結果資料に依拠)[出典2・6・9]。
6. 資格取得後の展望(臨床・研究・政策)
- 臨床栄養:急性期〜回復期・在宅、NST活動、がん・糖尿病・腎疾患などの栄養管理[出典1・5]
- 研究・教育:大学院での栄養学・食品学・公衆栄養学研究、教育職へのキャリア[出典1]
- 行政・公衆栄養:自治体での政策・事業の企画実施、特定保健指導の実施者としての役割[出典4]
まとめ
管理栄養士は、臨床から地域・政策・産業まで社会課題の解決に直結する高度専門職。最新の公的データに基づき、受験要件の把握→枠組みに沿った学習→実務に活きる思考で合格とキャリア拡張を狙いましょう。
参考・出典(正規URL)
- 厚生労働省|職業情報提供サイト(job tag)「栄養士・管理栄養士」:職務・就業先の全体像
- 厚生労働省|第40回 管理栄養士国家試験 受験要領(PDF):試験地・期日・受験資格、科目等
- (参考)東京都|管理栄養士国家試験 合格後の免許申請(最新案内・実務手続)
- 厚生労働省|特定保健指導(実施体制の考え方・医師/保健師/管理栄養士の役割)
- 日本栄養治療学会(JSPEN)|NST専門療法士 認定資格制度(制度の公式情報)
- 厚生労働省|第39回(2025) 合格発表(受験者16,169/合格7,778/48.1%・東京ほか計9地区で実施)
- 厚生労働省|第38回(2024) 合格発表(49.3%)
- 厚生労働省|第37回(2023) 結果PDF(56.6%、合格基準の確認にも有用)
- 厚生労働省|第39回 結果PDF(合格基準=120/200、区分別合格率:新卒80.1% 等)
お問い合わせ
無料体験のご依頼や、受験生活でのご相談、その他ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください
フォームでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
受付時間 10:00~18:00
(土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く)