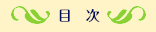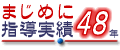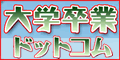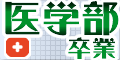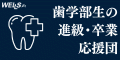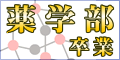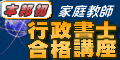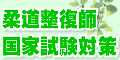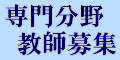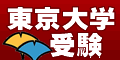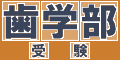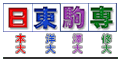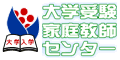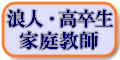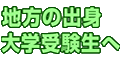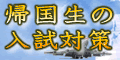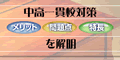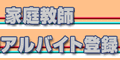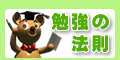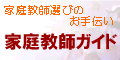栄養士から管理栄養士になるための考察

管理栄養士は、栄養学に基づく高度な専門知識を有し、医療・福祉・食品産業・行政など多岐にわたる分野で活躍する職種である。その業務は単なる栄養管理にとどまらず、個別化医療の推進、健康政策の策定、食品機能の評価、疫学的研究などにも及ぶ。とりわけ、病院・介護施設では、病態栄養学の視点から患者の栄養介入を行い、エビデンスに基づいた栄養管理を実践することが求められる。
さらに、食環境や社会文化的要因を考慮した食育活動、メタボリックシンドロームの予防に関する特定保健指導、スポーツ栄養分野でのパフォーマンス向上支援など、管理栄養士の職域は拡大し続けている。
1. 管理栄養士国家試験の受験要件
管理栄養士の資格を取得するには、まず栄養士の資格を取得し、さらに国家試験に合格する必要がある。
受験資格は、栄養士養成施設(短期大学・専門学校)または管理栄養士養成施設(4年制大学)を卒業したかによって異なる。
(1) 栄養士養成施設卒業者の実務経験要件
栄養士養成施設を卒業した場合、修業年数と実務経験の合計が5年に達することで受験資格が得られる。
具体的には、
2年制専門学校卒業 → 3年間の実務経験が必要
3年制専門学校卒業 → 2年間の実務経験が必要
(2) 管理栄養士養成施設卒業者の即時受験資格
4年制大学の管理栄養士養成課程を修了した場合、実務経験なしで管理栄養士国家試験を受験できる。
2. 実務経験の認定基準とその重要性
管理栄養士試験の受験資格を得るための実務経験は、以下のような業務に従事することで認定される。
医療機関・福祉施設:
病態栄養管理、NST(栄養サポートチーム)活動、個別栄養指導
学校・給食施設:献立作成、HACCP管理、食育推進
行政機関:地域栄養政策の策定、生活習慣病予防活動
食品産業:食品機能研究、商品開発、品質管理
実務経験の充実度は、試験合格後の即戦力としての資質にも大きく関わるため、単なる経験年数の充足だけでなく、臨床的・研究的視点を持った実践が求められる。
3. 管理栄養士国家試験の難易度と学術的対策
管理栄養士国家試験は、多分野にわたる専門知識が要求され、合格率は平均40~60%に推移する。ただし、栄養士養成施設卒業者の合格率は約20~30%と低く、4年制大学卒業者の50%以上と比較すると、独学による学習の限界が指摘される。
国家試験の内容は、
基礎栄養学・応用栄養学:
代謝機構、エネルギーバランス、疾病予防の栄養学的アプローチ
食品学・食品衛生学:
食品機能成分の作用、食品安全基準、微生物制御
公衆衛生学:
疫学的研究手法、健康政策、栄養疫学の応用
解剖生理学・生化学:
栄養素の生理学的影響、代謝経路、内分泌系との相互作用
これらの科目は相互に関連し、総合的な知識が要求されるため、体系的な学習戦略が不可欠である。

4. 効果的な学習法と個別指導の優位性
管理栄養士試験は、広範な知識が求められるため、効率的な学習計画が必要である。
(1) 科目横断的アプローチ
単独の科目学習ではなく、生化学と栄養学、公衆衛生学と疫学のように関連する分野を並行して学ぶことで、知識の統合が進む。
(2) 過去問分析と頻出分野の重点学習
過去10年分の出題傾向を分析し、特に計算問題や応用問題の頻出分野を重点的に学習する。
(3) 個別指導の有効活用
家庭教師による個別指導では、
専門家による論理的解説:試験問題の背景理論を深く理解
個別最適化された学習計画:受験生の弱点を補強するカリキュラム設定
実践的問題演習と解答技術の向上:長文問題の読解、計算問題の解法トレーニング
特に、働きながら受験勉強をする場合は、限られた時間で最大の効果を得るための戦略的学習が求められる。
5. 管理栄養士資格取得後の展望と学術的キャリアの可能性
資格取得後のキャリアは多様であり、臨床現場のみならず、食品機能研究、栄養疫学、政策立案など学術的視点を活かした分野でも活躍が可能である。
(1) 臨床栄養分野
病院・介護施設でのNST活動、がん・糖尿病・腎疾患患者の栄養管理
(2) 研究・教育分野
大学院進学による栄養学・食品学・公衆衛生学の研究、学術論文の執筆
(3) 行政・国際機関での政策形成
厚生労働省、WHO、FAOなどでの栄養政策の策定と実施
まとめ
管理栄養士資格の取得は、単なる資格取得にとどまらず、社会的課題の解決に貢献できる高度専門職としての道を開く。独学では到達が困難な領域も多いため、専門家による指導を受けながら、論理的かつ戦略的に学習を進めることが、合格およびキャリア発展への近道となる。
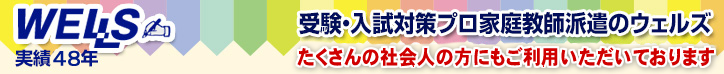

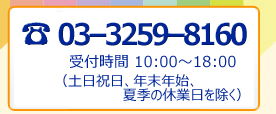

 本文へ
本文へ