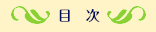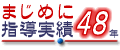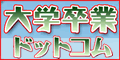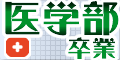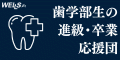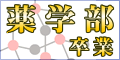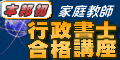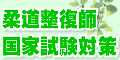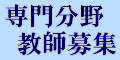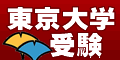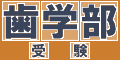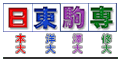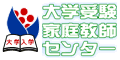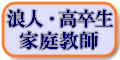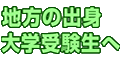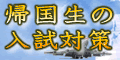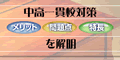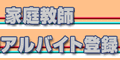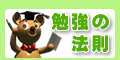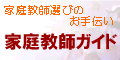【家庭教師で合格力倍増!】
管理栄養士国家試験最短攻略
―個別指導で実践力・応用力を徹底強化
管理栄養士国家試験の合格を目指すあなたへ――
最新の出題傾向は、単なる暗記ではなく実践的な応用力が求められる難関なステージへと進化しています。従来の勉強法ではカバーしきれない「実践力・応用力」を徹底的に鍛えるためのポイントを解説するとともに、個々の弱点に合わせた効率的な学習プランを実現する家庭教師サービスの魅力をお伝えします。個別指導により、あなたの学習のペースやスタイルに最適なサポートを受け、最短ルートで合格を手にするための戦略を、具体的な対策とともにご紹介します。

近年の管理栄養士国家試験では、試験内容の高度化と実践力がより強く問われる傾向があります。以下のポイントが、近年の国試対策における重要な対策点として挙げられます:
-
応用力試験対策の強化
・従来の基礎知識中心の対策に加え、実際の現場での判断力や応用力を問う長文・ケーススタディ形式の問題が増えています。
・選択肢を先に読む、重要なキーワードにマーカーを付けるなど、長文問題を効率的に解くテクニックが必要です。【例】長文ケーススタディの問題を解く際、まず患者の病歴や検査値(例えば、低アルブミン値や高血糖値など)を素早く把握し、何が問われているかを判断する練習を行います。例えば、糖尿病と高血圧、腎機能低下を併発した患者のケースで、どの栄養管理が最も適切かを複数の選択肢から選ぶ問題に挑戦し、選択肢の最後の一文とキーワードに注目するテクニックを身につけます。
-
重点科目の戦略的学習
・出題数や配点が高い「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」「臨床栄養学」「食べ物と健康」などの科目を、優先的に徹底的に学ぶことが重要です。
・論理的思考が必要な科目に重点を置き、知識を単なる暗記ではなく実務に結びつける学習が求められます。【例】「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」「臨床栄養学」「食べ物と健康」など、出題数・配点が多い科目に注力します。たとえば、人体の代謝経路や各器官の働きをまとめたノートを作成し、臨床栄養学では実際の患者ケース(例:心不全患者の栄養管理)のシミュレーションを繰り返すことで、知識を応用できるレベルまで引き上げます。
-
過去問・模擬試験の徹底活用
・最新の出題傾向を把握するために、過去問を繰り返し解き、間違いの傾向を分析することが不可欠です。
・模擬試験を通じて、試験時間の配分や本番の雰囲気に慣れることも得点力アップに直結します。【例】毎週、過去5年分の問題集から模擬試験を実施し、実際の試験時間(午前2時間25分、午後2時間40分)を意識したタイムトライアルを行います。模擬試験後は、間違えた問題の解説を徹底的に復習し、なぜその解答になるのかを自分なりに整理。また、スマホアプリなどを利用して、移動時間にも問題演習を行います。
-
基本知識の定着と最新情報のアップデート
・基礎栄養学や応用栄養学の基本事項は、応用問題を解くための土台です。しっかりと定着させた上で応用対策に取り組む必要があります。
・出題基準は約4年ごとに改定されるため、最新の栄養学の知見や現場のニーズを反映した教材選び・対策が大切です。【例】基礎栄養学や応用栄養学の重要概念をフラッシュカードやマインドマップで整理し、定期的に復習します。さらに、日本栄養士会や最新の学会発表をチェックし、最新の出題基準や栄養学の研究成果を取り入れた教材や情報をアップデート。たとえば、最新のガイドライン改定内容を反映した参考書を新たに購入し、勉強会でディスカッションするなど、知識のブラッシュアップを図ります。
効率的な学習計画とマインドセット
・短期間で合格を目指す場合、QB(クエスチョンバンク)や過去問集の分解学習、復習のタイミングの工夫など、効率的な勉強法がカギとなります。
・また、試験本番に向けた前向きな心構えや、計画的に学習を進めることが成功への大きな要素です。【例】1日の学習スケジュールを朝・昼・夜に分け、朝は新しい内容の習得、夜は模試や復習に充てる計画を立てます。たとえば、毎朝2時間、夜に1時間の勉強時間を確保し、週ごとに達成目標(模試で80%正答など)を設定。さらに、家庭教師と定期的に面談し、進捗に応じて計画を修正。モチベーションを維持するため、目標達成時には自分にご褒美を設定するなど、前向きなマインドセットを保つ工夫も取り入れます。

管理栄養士国家試験の難易度が上昇する中、合格への鍵は「実践力」と「応用力」を如何に効率的に身につけるかにかかっています。この記事でご紹介した各対策ポイントを、家庭教師の個別指導で徹底的にブラッシュアップすることで、あなたの弱点を克服し、得意分野をさらに伸ばすことが可能です。
合格への近道は、効率的な学習計画と専任の指導者による戦略的なサポートにあります。
ぜひ、家庭教師サービスを活用して、あなたの合格力を倍増させ、夢の管理栄養士資格取得を実現してください!
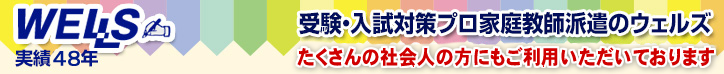

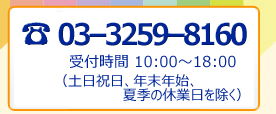

 本文へ
本文へ